
人を知る クロストーク#2 ライフイベントとキャリアの両立
Introduction
産前・産後休暇や育児休暇を取得して復帰した2人の社員と、人事企画部で制度を構築している担当者がクロストーク。制度を使った感想、育児と仕事の両立、そして望むキャリアの実現などついて語り合ってもらいました。3人の声を通じて、野村證券で働くリアルを映し出します。
Member

小泉 有加 Koizumi Yuka

野口 孝太 Noguchi Kota

芳谷 剛伸 Yoshitani Takenobu
※所属部署・掲載内容は取材当時のものです。
Cross Talk

Talk Theme 1
産休・育休を取得したきっかけとタイミング

小泉
明確なイメージがあったわけではありませんが、入社前から入社後数年は、結婚して子どもが生まれたら仕事を辞めるという選択肢も持っていました。ただ、できることが増えて仕事がとても楽しくなっていったこと、さらにビジネスモデルの変革を通じ、ストック型ビジネスへの転換が進み、会社の環境も変わったことで、出産後も育児をしながら仕事を前向きに続けたいという気持ちが高まっていきました。今は産休・育休を経て復帰し、1歳の子どもを育てながら働いています。

野口
私も具体的なライフプランは持っていませんでした。子どもが生まれてからもしばらくは育休を取得していなかったのですが、家族で過ごすうちに少しずつ一緒にいる時間がほしいと思うようになり、比較的珍しいタイミングかもしれませんが 、子どもが2歳になる直前に育休を取得しました。

芳谷
もともと野村には、男女関係なく子どもが2歳になるまで育休を取得できる制度はありましたが、実際に取得しているのは女性ばかりでした。心理的な障壁を取り除くために、取得を全面的に推奨するよう制度を拡充してからは、男女を問わず取得率が高まってきたと感じています。野口さんが育休を取ろうと決めたきっかけは何ですか?

野口
まさに、その制度拡充を知ったことです。子どもが生まれた時点で「どこかのタイミングで育休を取得したい」と上司に相談はしていたものの、義母がサポートしてくれたこともあり、その後取得することなく日が過ぎていました。しかし、休業中の給料を補償する奨励金制度(※)が設けられたことを知り、この機会に活用したいと上司に相談しました。
※育児休業取得奨励金:連続1か月以上の育児休業を取得した場合、復職後に所定の申請を行うことで一定額が奨励金として支給されます。

芳谷
休むと迷惑をかけるのでは、という周りへの遠慮や収入面の不安を解消したいと思って拡充した制度です。私の部でも最近3名の男性社員が育児休業を取得しました。制度が活用されていることを実感でき、うれしい限りです。

Talk Theme 2
育休取得と評価・キャリアの関係性

芳谷
育休を取得するにあたって、大変だったことはありませんでしたか?

小泉
産休取得前はつわりがひどく、思うように出社できないこともありました。ですが、時間単位で使える有給休暇や傷病等休暇をうまく活用でき、出社日数を調整しながら対応できました。それに、課員と一緒に仕事を頑張りたい気持ちとそれに追いつかない体調、その両方に上司が配慮してくださったことが心の支えになりました。業務は課員に振り分けて任せることを意識したことで自分の仕事量を調整できましたし、結果的に課員の成長にもつながったと思います。

野口
私の上司も産休・育休を経て今のポストに就いている方で、取得を全面的に勧めてくださいました。育休取得が今後のキャリアにネガティブに響くのではないかという不安もあり、正直に相談しましたが、それだけでマイナス評価につながることはないと明確に答えてくださったおかげで思いきって休むことができました。

芳谷
実際に育休を取得してみて、もともと感じていたキャリアへの不安はいかがでしたか?

野口
日々の業務において受けるフィードバックや、期中・期末の評定結果を見ても、今回の育休取得が評価に影響を与えることはなかったと安心しています。復帰後も、子どものお迎えなどで勤務時間の調整が発生することがありましたが、上司は業務の成果と個々の実力で正当に評価してくれますし、課内での助け合いで仕事にもしっかり対応できています。上司だけでなく、課全体にそれを当然のこととする雰囲気が醸成されていると感じます。私は育休取得後に昇格したのですが、それも純粋に仕事のパフォーマンスを評価いただいた結果だと感じています。

小泉
私も復帰直後に昇格したので、仕事場での成果を評価してくださっていると思います。産休育休前までに頑張ってきたことがゼロになるわけではなく、逆に現在育児中だからと甘やかされることもなく、とてもフェアに接してくれます。「育児中でも仕事に一生懸命取り組み新しいことにチャレンジしたい」という、私が望む復帰後の働き方を、支店長とのコミュニケーションを通じて理解していただけていると思います。実際、復帰後から産前と同様に課長席を任せていただき、新しいプロジェクトも課として参加させていただき、期待をかけてくださっています。

芳谷
それを聞いて安心しました。7年ほど前、全支店を回って社員にインタビューを実施する機会があり、出産・育児等の様々なライフイベントと仕事を両立しながら頑張る社員たちの姿がとても印象的でした。野村は従来からライフイベントや環境の変化を迎える社員の活躍をサポートする取り組みに力を入れてきましたが、近年は福利厚生制度の拡充やカルチャーの浸透も一層進み、ますます「誰もが自分らしく成長し、ポテンシャルを最大限に発揮できる環境」が実現できているのだなと、嬉しく思います。

小泉
はい!みんなと一緒に新しい仕事に挑戦することを楽しんでいます。

Talk Theme 3
仕事と育児の両立を叶える野村證券の文化

野口
普段は子どもの入浴を担当しています。21時ごろには就寝させたいので、そのためにも20時までには帰宅したい。毎日できる限りその時間に間に合うように仕事を終わらせ、家族の時間を大切にしようという意識が強くなりました。

小泉
仕事のスケジュールを自分で柔軟に調整できるので、メリハリの効いた働き方ができますね。家族とも協力し、たくさんサポートもしてもらっています。 私も、出社している間は最大限のパフォーマンスを出すようにして、帰宅後や休日には子どもに、めいっぱいの愛情を注いでいます。

野口
課のメンバーの半数が子育てをしながら働いていることも、仕事と育児を両立しやすいポイントの一つです。最初は休むことに対して心理的なハードルがありましたが、それぞれが子どもの学校行事や発熱などで時間休(※)を取得して仕事を抜けることが日常的にあり、言い出しにくい空気がありません。お互いにカバーし合おうという共通認識が醸成されていて、恵まれた環境だと常々感じます。
※野村證券では年次有給休暇を1時間単位で取得することが可能です。(利用上限あり)

小泉
私の職場も育児をしながら働いている方が大半なので、マイノリティにならず、相談しやすいです。育児だけでなく病気や介護などそれぞれの事情もあると思うので、私自身がやるべきことをやりながらも人に頼ることで課員も頼りやすい環境を作ることを心がけています。

芳谷
これまで、制度の利用は進んでいるものの、現場ではしっかり助け合いができているのか不安がありました。ですが今のお二人のお話を聞いていると、実際にみんながサポーティブに動いてくれていることを実感します。お互いさま文化が根づきつつあるのでしょうね。

野口
そう思います。ただ、サポートを当たり前と思わず、感謝することは意識しています。そして仕事で活躍して課に貢献し、周りの人が助けを必要とした時にはしっかりサポートする。その気持ちは持ち続けていたいですね。

小泉
同感です。感謝の気持ちがあるからこそ成り立つ環境だと思います。

芳谷
頼もしいです。誰か一人が休むと仕事が回らない、という状態は組織のあり方としてよくないので、そうならない体制づくりは組織のマネージャーに任されていることですが、一方で、助け合いの部分は一人ひとりの気持ちによるところが大きいもの。それが文化としてしっかり醸成されると、野村はもっと強い組織になると思います。

Message
さらに働きやすい環境をつくるために

芳谷
もともと、ゴールに向かってみんなが同じベクトルで突き進む突破力が野村の強みでしたが、これから一段上のステージに上がるためにはそれだけでは足りません。組織が成長し続けるには、一人ひとりが自分の意見を持ち、異なる意見も取り入れながら一緒に最適解を見つけていくことが必要であり、そのためには多様性のある組織作りや、それぞれに異なる事情や価値観を持つ人を受け入れるインクルージョン(包括性)が重要です。その最たるものが男女差をなくすことであり、女性活躍や男性の育休取得を促すことだと思っています。

小泉
多様性という点では、育児を優先したいのか、仕事にも全力を出したいのか、望む働き方は人それぞれなので理解し合うことが大切ですね。良かれと思って負荷の少ない仕事を任せても、本人はもっと頑張りたいと思っているかもしれません。生活背景もそれぞれ違います。私のチームでは毎月1on1ミーティングを実施し、仕事上では言いにくいことも相談してもらえる場を設けて相手を理解することを大切にしています。

野口
よく分かります。育児が大変だからと業務量を落とすことを良いと思う人もいれば、物足りないと感じる人もいるはず。本人と周りのメンバーとのコミュニケーションで、その認識のずれをなくすことが働きやすさにつながると思います。

小泉
一方で、制度面はすでにとても充実していて、それぞれが望む働き方を貫ける環境があると思います。例えば、勤務時間を柔軟に調整できる「育児時間」や、託児所利用の費用補助、ベビーシッター券などですね。価値観は人によって違うので、皆さんがたくさんある制度の中から自分に合ったものを選択して使われています。

野口
最近私は、芳谷さんが制度紹介をしてくれているメール配信で、つみたてNISAに対する奨励金がアップしたことを知り早速申請しました。他にも、従業員持株制度への奨励金や保険への手厚い補助など、経済的なサポートもかなり充実しています。知らずに活用できないともったいないので、ぜひみなさんに知っていただきたいです。

芳谷
働きたい人は働く、休みたい人は休むという、個々が望む働き方を実現することが制度のコンセプト。育児に限らず、ライフステージの変化に伴って仕事を調整せざるを得ない場面は誰にも出てくるので、ステージごとにサポートし、ずっと働き続けられる会社にしたいですね。

Message
それぞれが叶えたい未来のために

野口
子どもには将来、自分のやりたいことに思いきり挑戦してほしいと願っています。本人の選択肢を制限することがないように、私は今の仕事を頑張って経済面でもメンタル面でも余裕を持っていたいですね。子どもに誇れる仕事をして、背中を押して支えてあげられる父親でありたいと思っています。

小泉
私も、子どもが自分なりの軸を持ってやりたいことを考え、実現できるように支えていくことが望みです。仕事面では、いつどんなライフイベントが発生しても、誰もがチャレンジすることを諦めなくていい職場を率先して作っていきたいと思います。

芳谷
働き方や組織のマネジメント、お客様との接し方など、全てにおいて野村は年々進化し、時代に合わせてどんどん良くなっていると感じます。人事組織内でも、次世代の方々にとって働きやすいカルチャーを根付かせていこうと話し合っています。変えるべきところ、変えずに守り続けるところを見極めながら、さらに会社が成長できるように一緒に環境を作っていきましょう。

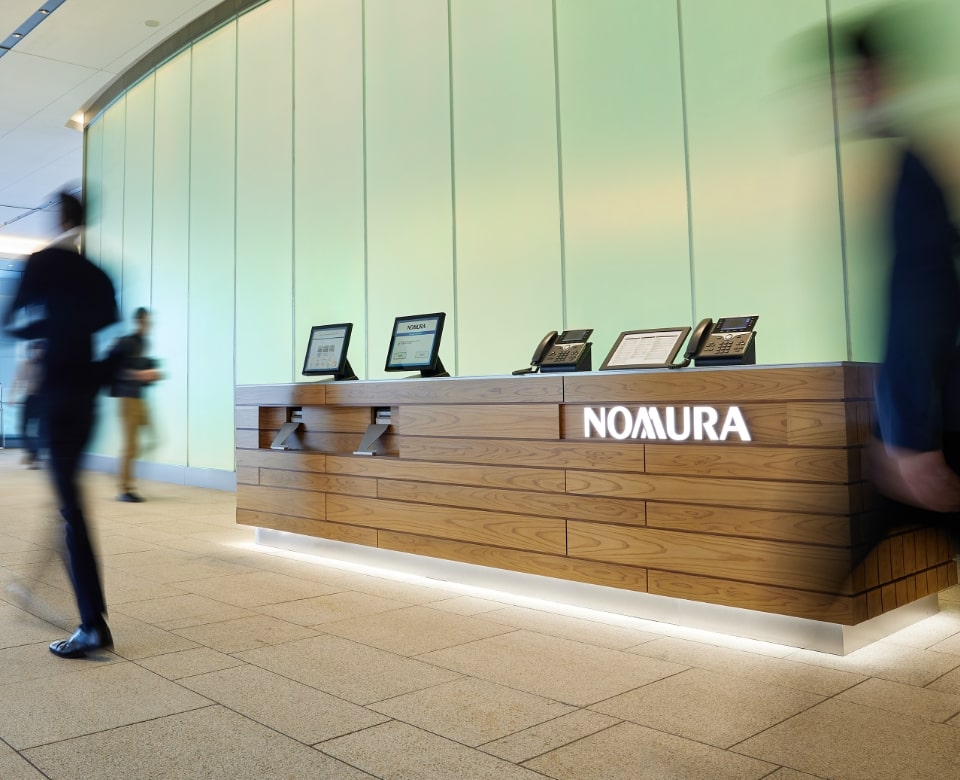










芳谷
私には大学生の子どもが3人いるので、制度を作る時にはいつも「将来、子どもたちが働く時に、自分たちが求めるライフプランを実現できる制度か」ということを考えながら、制度を整えてきました。小泉さんは産前産後休暇と育児休暇、野口さんは育児休暇を取得されましたが、もともとどんなライフプランを思い描いていましたか?